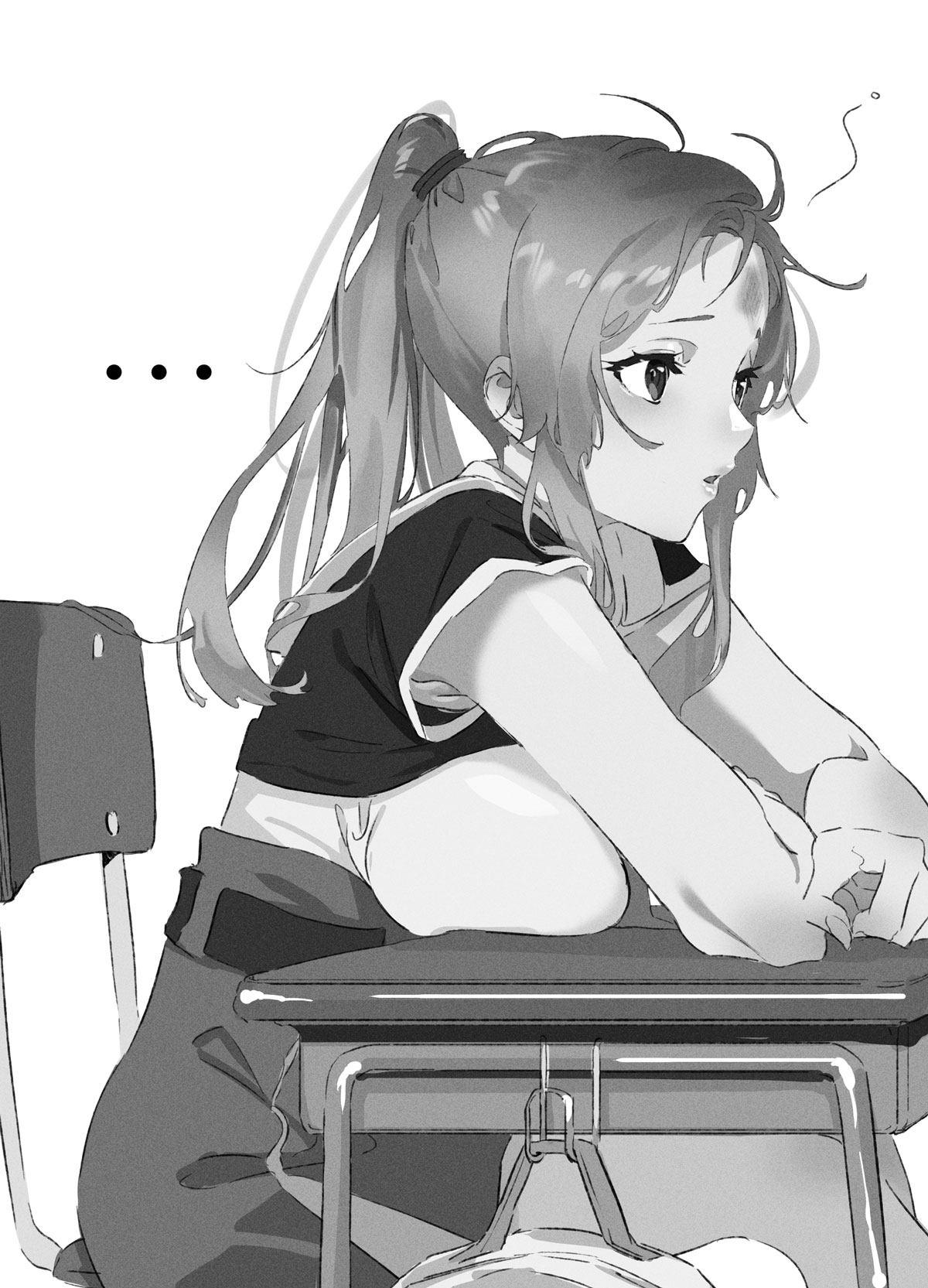二、凡田純一 その2
3
チェックは全てクリアだった。
事件は起きていない。住居に侵入されてはいない。郵便物はいじられてはいない。
それなのに次から次に懸念が押し寄せてくる。
下校時に見かけたあの男、どこかで見たことがある。それは当たり前だ。自分だけがアーケードに出入りしているわけではない。同じ場所にいれば、見る顔も同じである。
通りかかったステーションワゴン。あのナンバーも見たことがある。もしかして尾行されている? しかし、あれはこの付近にある実在の会社だ。住所も登記も確認してある。それに同じナンバーを見るのはあの車だけではない。何度も検討し、そう結論を出したはずである。
『朝の挨拶運動』は、本当に偶然だったのか?
何かの偶然だったのか、橘黒姫がわずかにこちらに寄ったような動きを見せなかったか?
この世界に偶然は存在しない。
臨場においては、常に周囲に疑念の目を向けることが生命線であった。
この世界に偶然は存在しない。
もっと感覚を研ぎ澄ませろ。何か兆候はなかったのか……!
フラッシュバックが起こった。
砂漠、密林、コンクリートの檻。人の目。目。目。全ての目がこちらを見つめている。疑っている。自分の正体を見抜いている……。
突然の、偏頭痛。凡田は机を離れ、洗面所に入り、流した水に頭を突っ込み、頸椎に水を浴びた。
自分が偏執症だということは間違いない。
常に誰かに監視されているような気がする。気がするだけだ。努めて普通に振る舞っているはずである。振る舞いに傷はないはずである。
客観的な事実はない。物証はない。
それなのに、懸念が離れようとしない。本能は告げている。何者かに監視されていると。
逃げるか、留まるか。結局、それが問題だった。
逃げることとは全てを台無しにすることである。
偽装経歴の鎖の輪は多方面に渡っている。自分が離脱すれば、それは他の輪に影響を与えてしまうことになる。
また、動くこと自体が目を引く可能性がある。プレッシャーに反応し、逃げたのなら、それは答え合わせになりかねない。
逃走資金の枯渇。それも判断を遅らせている原因の一つだった。
逃走資金はほとんど残っていない。偽装の形成、整形費用、物資調達に消えてしまった。もう一度、偽装を作り直し、別人になりきることは不可能である。
今の自分に正確な判断が出来ているのか?
単独行が判断に悪影響を与えていることは間違いない。
今までも単独潜行の経験はあった。しかし、今の状況はそれとは全く違う。補佐してくれる人間はいない。組織のバックアップもない。あらゆるものを敵に回し、全て自分で考え、判断しなくてはならない。
六畳のフローリングに戻った。
嘘で満ち溢れた空間。雑多な物品は、どれも『凡田純一』という人間を実在させるために必要な物だった。偽装に必要なものを削ぎ落としていく。そこには何も残らないだろう。
それでも。
ここには自分の望むものがあった。
自分の望む、全てのものがあった。
4
夜十時。パーカーを羽織り、凡田はマンションの裏口を出た。
近所には大学のキャンパスがあり、この時間であってもまだ人通りは多い。それが、このマンションを選んだ理由の一つでもあった。
凡田は夜間の外出には自転車を使わないことにしていた。職質の際、防犯ナンバーを控えられるためである。徒歩であっても職質の危険性はあったが、今のところは上手く逃げ続けている。最悪、そういったときに備え、偽装した私大の学生証を用意してあったが使わないに越したことはない。
やがて、駅前のゲームセンターに辿り着いた。
地下一階、人はまばらだった。風営法対策のダーツエリアを抜け、凡田はカードゲーム筐体の近くにあるトレード掲示板の前に立った。
自分が書いた用紙を見る。
『SRダヴー⇔Rマリー・アントワネット』
いわゆる鮫トレである。レアリティで言えば一見、大幅に譲歩しているように見えるが、こちらが提示しているのは旧弾の特に人気のないカードであり、トレード候補に挙げているのは新バージョンの中でも特に環境を席巻している、しかも女性のイラストの人気カードである。レアカードの希少性を全く考慮しないアンフェア・トレードであり、通常なら全く反応がないのが当然のオファーだった。
しかし、自分が書いた紙に、誰かが書き込んだ跡が残されていた。それを確認すると、リズムゲームのコーナーに移る。荷物置きのプラスチック籠に景品用のビニール袋を入れた。
ゲームをプレイしていると、やがて、一人のプレイヤーが隣の台に立ち、凡田と同じように景品用のビニール袋を置いた。視線は向けなかった。先ほど姿は確認してあった。スカジャンにベースボールキャップ。ゲーム音に紛れ、ハスキーな声が聞こえてきた。
「うーっす、デブりん」
コインを投入すると、こちらのコンパネに凡田のトレード用紙を置いた。
「不勉強じゃないの? 先週バージョンアップがあって大幅下方が入ったんだから、これだとうっかり成立するかもしれないよ」
女の名は
真仁はこちらの素性は知らない。ただの客の一人、あるいはこちらも繋ぎだと考えているだろう。
『デブりん』というのは真仁が勝手に呼んでいる愛称である。こちらが名乗るのを拒んだため、そう呼び始めたのだ。
ゲームを続けながら、会話を交わす。
「で、何が欲しいの?」
「
「あれを?」
それだけで通じたようだ。
KSGは主にモデルガンを扱っている模型メーカーである。このメーカーの制作したハイボルテージ・シリーズはシリンダーに収めた薬莢形のカートリッジにBB弾とガスを注入する構造になっており、リアルな造形も相まって人気を集めたモデルガンである。
しかし、後になって簡単な補強によって二二口径弾が発射できることが判明し、警察からの指導で販売中止となったモデルである。
「そういうのだったらもっといいのあるけど? ホンモノのほうがよっぽど安いけど」
「必要ない」
「あっそ、まあ、うちのに言えば手に入ると思うけど」
「いくらだ?」
「三十」
「…………」
沈黙すると、真仁は笑った。
「高いとは思わないけどなー。あれ、もう廃版だから手に入らないと思うけど。まあ、それが嫌ならヤ○オクでもメ○カリでもやったら? うちは困らないし」
「……前金で十持ってきた」
「毎度ありー」
最上級譜面をきっちり完走して、真仁は凡田の持ってきた袋を掴み、その場を立ち去った。
帰り道、駅近くの高架下に差し掛かった。
街中にぽっかりと口を開けた、空白地帯。大通りを行く車のヘッドライトがときおり、闇の中に浮かぶ薄汚れた
俺は何をしている? いつまでこんな中途半端なことを繰り返すんだ?
本来であれば、銃など傍に置いておきたくはなかった。銃が必要になるような危機をあらかじめ回避するのがこの逃走における自分の方針だったからである。改造モデルガンというのはどっちつかずの選択肢だった。
それでも武装という誘惑に勝てず、例外中の例外を認めた。
作戦に例外が紛れ込むとき、それは破綻に向かっていることがわかっていながら。

◆
「それじゃ、先にお昼どうぞ」
「はーい」
小さな歯科医院。
歯科助手が財布を手に表へ出て行くと、診察室には自分と患者だけとなった。ピンク色の紙エプロンをした患者は目にタオルを掛けられ、診療台に仰向けになっている。
「…………」
歯科医はそれを一瞥すると、荷物置きにある患者の鞄に手を掛けた。中にある黄色いファイル。それを取り出すと、白衣の中に忍ばせていたファイルと取り替え、鞄に戻した。
さりげない仕草でファイルを机の引き出しに収めると、診療台へと戻る。
「見た感じ奥歯がガタガタですねえ。お仕事大変なんですか?」
「余計なことはいい」
患者、《御伽衆》の
「上はもっと詳細な情報を求めている」
歯科医は渋面を浮かべると同時に、胃がきりきりと痛み始めた。直接の会話は通常ルーティンにはない。それは上層部の焦燥を意味し、同時に自分の窮地を意味している。
歯科医は声を落として返した。
「お言葉ですがこれ以上は無理です。現場からは、ただの監視だけでは今以上の情報を集めるのは不可能だと……」
「作戦の方針は聞いているはずだ」
知っている。接近厳禁、接触厳禁、住居侵入など非合法活動厳禁。組織がそれでやれという以上、それ以外の方法はない。
「せめてこの作戦の目的を教えてください。上は何を欲しがっているんです? それがわからなくてはやりようがありません」
「…………」
〈雉〉はタオルを除け、こちらを見返してきた。機械のような目。それはこう言っていた。
組織に対する詮索は、死あるのみ。
歯科医院はどこにでもある。誰でも虫歯になるから、出入りを疑われることもない。工作員が偽装するにはうってつけの場所だった。
歯科医の役目は『手配師』あるいは『
この道に入って十年近く経つ。それなりに経験は積んでいるつもりだった。
それでも今回のような異様な作戦は初めてだった。
ただの男子高校生を追跡。二十四時間態勢で監視すること。
目的は不明。しかも厳しい制約が付いている。一言でいえば、遠巻きに眺めるだけで詳細な情報を得ろというのだ。そもそも相手はただの高校生である。上がってくる情報もたかが知れている。
それでも組織は執拗に情報を欲していた。乾ききったスポンジから存在しない水滴を絞りだそうとするように。
歯科医は空になった診療台を見下ろしていた。
組織の力は嫌というほど知っている。
詮索は死。不履行は死。
実際に、粛正にあった人間を知っていた。組織に背いたゆえに、あるいは無能ゆえに。
このまま手をこまねいていた場合、自分に待ち受けているものが、決して明るいものではないことはわかりきっていた。だが、これ以上、どうしろというのか……。
そのとき、記憶の隅に小さな灯りがともった。
一人、使えそうな人間がいた。
素性を隠したまま社会に潜り、作戦決行のそのときまでただの市民として過ごす。機密のために組織に対しても秘匿され、切り離された存在。
四年前、そのスリーパーの一人を前任者から引き継いでいた。
何故、今それに思い当たったのかといえば、そのスリーパーが関わっていた作戦が凍結になったからだ。前任者によれば、作戦責任者が死亡したために作戦自体が無期延期、人員の処遇に対しては追って指示があるだろう、とのことだった。
だが、指示はいつまでも来なかった。組織からも忘れ去られたかのように、いつまでもそのスリーパーは配置転換から漏れたままだった。
歯科医はあえて上に報告しなかった。特に考えがあったわけではない。使えるカードは持っておく。この世界の人間が皆するように、自分もそうしただけだ。いつか、そのスリーパーが役に立つときがくるかもしれない、そう思って。
そのときが来たのかもしれない。
自分が知っているのは連絡手段などの概略だけだが、スリーパーの年齢はわかっていた。十七歳。監視対象と同じ年齢。
スリーパーを作戦目標に直接、接触させる。
密かに、組織にも知らせずに。それならば新たな情報を得ることができるだろう。
だが、これは明確な作戦規定違反だ。もしそれが発覚したとしたら……。
わかりはしないだろう。責任者も、前任者もすでに死亡している。そのスリーパーの生活に必要な資金などの流れも、組織の複雑なシステムのために全容を把握するのは不可能。現状、そのスリーパーを認識しているのは自分だけだ。
どのみち、自分に残された道はそれしかないのだ。
組織は裏切りを許さないが、それ以上に、無能には不寛容なのだ。
◆
「よくできましたね」
先生はそういった。
近接戦の授業のときだった。先生はあたしの目の前に膝を突き、こちらを見上げていた。
「もう、あなたに殺せない人間はいません。あなたの手が触れたのなら必ず殺すことができる。どんな人間であっても。どんな怪物であっても」
先生はそういって、わらった。
先生の手は赤くぬれていた。先生の服は赤くぬれていた。
「あなたは最高の生徒です。最高の暗殺者です。私よりも、ずっと強くなった」
先生は少し、せきをした。
先生はあたしの先生だ。殺すことの先生だ。ナイフの使い方、銃の使い方、体の使い方。あたしはいろんなことを教わった。
「もっと色々と教えたかったけれど、もう時間がないみたいですね」
先生はとても怖かった。
でも、そのときだけは妙に優しくて、だからよけい怖かった。
「
先生はあたしの名前を呼んだ。
「最後に、私のお願いを聞いてください」
最後? 次の授業は? 明日は? これからあたしは誰の言うことを聞けばいいの?
「一度だけです。あなたが殺すのは一人だけです。あなたの手であの怪物を終わらせるのです。私の代わりに」
先生はぬれた手であたしの頬にふれた。生温い空気、生暖かい匂いが顔を包んだ。
「そのときまであなたは眠り続ける。あなたは生まれ変わる。新しい人間に。ここであったことの全てを忘れ、そのときのために穏やかに眠り続ける。あの怪物が、あなたの手の届くところに現れるまで……」
あたしは生まれ変わる? ここからいなくなるの? これからどうなるの?
先生はそれには答えてくれない。先生は目を閉じた。だんだん、息がほそくなっていく。
「あなたの新しい名前……あなたの名前は……」
「
誰かに呼ばれ、明希星は目を覚ました。
「…………」
記憶があやふやで、しばらくぼうっと周りの景色を確認した。
暖かい日差し。白いカーテン。教室。黒板。くすくす、という笑い声。
そうだ。
芹沢明希星は私の名前だ。
今のは夢で、私は子供じゃなくて、私は高校生で、ここは学校で、それで授業中で、今のは夢だったから、私は眠っていて……。
それ以外の状況は全くわからない。
とりあえず頭を上げ、明希星はこたえた。
「……スミマセン。聞いてませんでした」